文部科学省が9月26日、保護者からの過剰な苦情対応を「学校以外が担うべき業務」とする指針改定を発表した。
一見理想的な方向性だが、教育現場の実態は複雑で、真の働き方改革には多くの課題が残されている 。
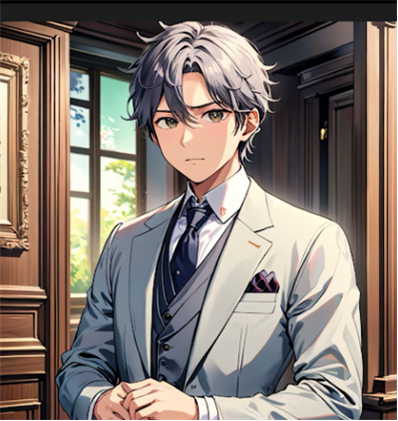

指針改定の背景と内容
深刻化する教員の精神的負担
2023年度に精神疾患で休職した公立学校教員は7,119人となり、3年連続で過去最多を更新した。
全教員に占める割合は0.77%(130人に1人)に達している 。
休職要因の調査では「児童生徒への指導に関する業務」が26.5%で最も多く、「職場の対人関係」23.6%、「事務的業務」13.2%と続いている。
文科省の調査によると、保護者対応が精神疾患による休職要因の6.3%を占めることも判明した 。
業務の3分類による整理
今回の指針改定では、教員業務を以下の3つに分類した :
- 学校以外が担うべき業務:保護者からの過剰な苦情・不当要求、登下校時の見守り、学校徴収金管理など
- 教員以外が積極的に参画すべき業務:ウェブサイト管理、ICT機器保守、施設管理など
- 教員業務だが負担軽減を促進すべき業務:給食時間対応、授業準備、行事運営など
残業時間については、従来の「月45時間以内」に加え、「平均月30時間程度」という新目標を設定した 。
現場が抱える構造的ジレンマ
初期対応の重要性という現実
私自身の経験だが元中学校校長として最後の年を務めた際、2つの学年で重大な生徒指導案件が同時発生していた。
現場では「初期始動時が最も大切」という原則がある。
この段階で手厚い保護者対応を含む十分な処置を怠ると、問題が大きくなり結局は教師自身の首を絞めることになる。
重大な生徒指導問題では、午後7時過ぎの家庭訪問、場合によっては保護者が帰宅する夜9時以降の対応も必要になる。
結果として、深夜12時まで対応することもある。
このような案件が複数同時発生していたので、校長として随時判断できる体制を整えるため、学校に待機し続けることになった。
退職前の3か月間、帰宅時間が午後10時を回ることが続いた。
各学年の教師も、家庭事情の許す限り学校に残って対処せざるを得なかった。
これはただ働きであることは明白だが、「問題を無視して帰ってしまえ」とは現場責任者として言えないのが実情だ。
現場の矛盾した状況
県からは「校長は○○時間以上の超過勤務をさせてはいけない」「勤務実態を報告するように」との通達がある一方で、実際に必要な業務時間は確保しなければならない。
教師も、自分たちの首を絞めることになると理解しているため、必要な用事がない限り自ら残って問題処理にあたらざるを得ない。
現役教員約5,200人を対象とした2025年の調査では、「約9割が隠れ残業」「平均11時間勤務」という実態が明らかになっている 。
この数字は、公式な働き方改革の掛け声とは裏腹に、現場の深刻な状況を物語っている。
私自身の肌感覚で実態はわからないながら、『カウンセリングを受けなければならないとされる90時間、100時間を超える残業』も、そうめずらしくはないだろうと感じていた。
指針と現実のギャップ分析
初動対応を軽視できない理由
生徒指導における初期対応の重要性は、教育現場では常識とされている。
大阪府の「いじめ初期対応のてびき」でも、早期解決のための5つのポイントとして、被害生徒のケア、組織対応、情報収集、指導体制構築、保護者連携を挙げている 。
問題を放置すると:
- 被害を受けた子どもが「先生は助けてくれない」と感じる
- 加害者側に「やっても大丈夫」という誤ったメッセージを送る
- 問題が深刻化し、より多くのリソースが必要になる
- 学校全体への不信が拡大する
「過剰な苦情」の線引きの困難
文科省は保護者からの「過剰な苦情や不当な要求」を学校外対応とするが、何が「過剰」で何が「正当」なのかの明確な基準は示されていない。
保護者にとって子どもの問題は切実で、学校側から見れば「過剰」に映る要求も、保護者の立場では「当然の権利」である可能性がある 。
実際の現場では:
- 子どもの安全に関わる緊急性のある案件
- 教育方針への疑問や提案
- 他の保護者との関係調整
- 進路相談や学習支援要請
これらの多くは、初期段階では「正当な相談」として始まり、対応が不十分な場合に「苦情」へと発展することが多い。
真の改革に必要な視点
体制整備の具体化が急務
指針では教育委員会への窓口設置や弁護士活用を求めているが、具体的な体制作りは各自治体に委ねられている 。
実効性を持たせるには:
- 専門職員の常駐配置:生徒指導専門員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの拡充
- 24時間対応体制:緊急案件に対応できる夜間・休日サポートシステム
- 教育委員会との連携強化:重大案件での迅速な外部機関連携体制
- 適正な人員配置:一人の教師に過度な負担を集中させない仕組み
一言でいうと、現場には人が足りない。
教師の職業倫理との両立
教師は「生徒を見捨てられない」という強い職業倫理を持っている。
この価値観は教育の質を支える重要な要素だが、同時に過重労働の温床にもなっている。
改革では、教師の献身的な姿勢を活かしつつ、構造的な問題解決が必要だ。
具体的には:
- 初期対応体制の外部化:緊急時対応専門チームの設置
- 役割分担の明確化:教育的指導と事務的対応の分離
- 継続的な研修:効率的な問題解決手法の習得支援
保護者との関係性再構築
保護者対応の外部委託は、学校と家庭の関係性を根本的に変える可能性がある。
建設的な協力関係を維持するには:
- 相互理解の促進:保護者向けの学校運営説明会の充実
- 対話チャネルの多様化:定期的な意見交換会、アンケート調査の活用
- 早期相談の推奨:問題が深刻化する前の気軽な相談環境作り
今後の課題と展望
財政的裏付けの必要性
働き方改革を実現するには、人員増や外部委託のための予算確保が不可欠だ。
文科省の指針だけでは、自治体の財政状況によって格差が生まれる可能性がある。
教員養成・研修制度の見直し
新しい業務分担に対応するため、教員養成課程や現職研修の内容見直しも必要だ。
効率的な業務処理、ストレス管理、外部機関との連携などのスキル習得が求められる。
これも、私見だが私が現役時代には「学校カウンセラーが学校に居ても、あまり役に立たなかった」という印象がある。
表現が不適切かもしれないが、「生徒がカウンセリングを積極的に望まない」(人間関係を作れない)
時間通りに来て、時間通りに帰ってしまうので、児童生徒たちや先生方と人間関係が作れないように感じていた。
しかも給料が高い。
これなら、『代わりに一般の非常勤講師を二人ほしい』というのが本音だった。
継続的なモニタリング
改革の実効性を確保するため、定期的な実態調査と改善策の検討が必要だ。
数値目標だけでなく、教師の満足度や子どもたちの学習環境の質的評価も重要な指標となる。
まとめ
文科省の指針改定は理想的な方向性を示しているが、教育現場の複雑な実情を踏まえた実効性のある改革にするには、まだ多くの課題が残されている。
特に、生徒指導における初期対応の重要性と教師の職業倫理を理解した上で、構造的な問題解決に取り組む必要がある。
真の働き方改革は、単なる業務分担の見直しではなく、教育の質を維持・向上させながら教師の働く環境を改善する総合的な取り組みでなければならないのだ。
そのためには、政策立案者、教育委員会、学校現場、保護者が連携し、継続的な改善努力を続けることが不可欠。
現場で40年間近く教師として、校長としても10年以上働いた経験から言えることは、理想と現実の間には大きなギャップがあるということ。
しかし、そのギャップを埋める努力を続けることこそが、子どもたちのより良い教育環境を作ることにつながるだろう。
