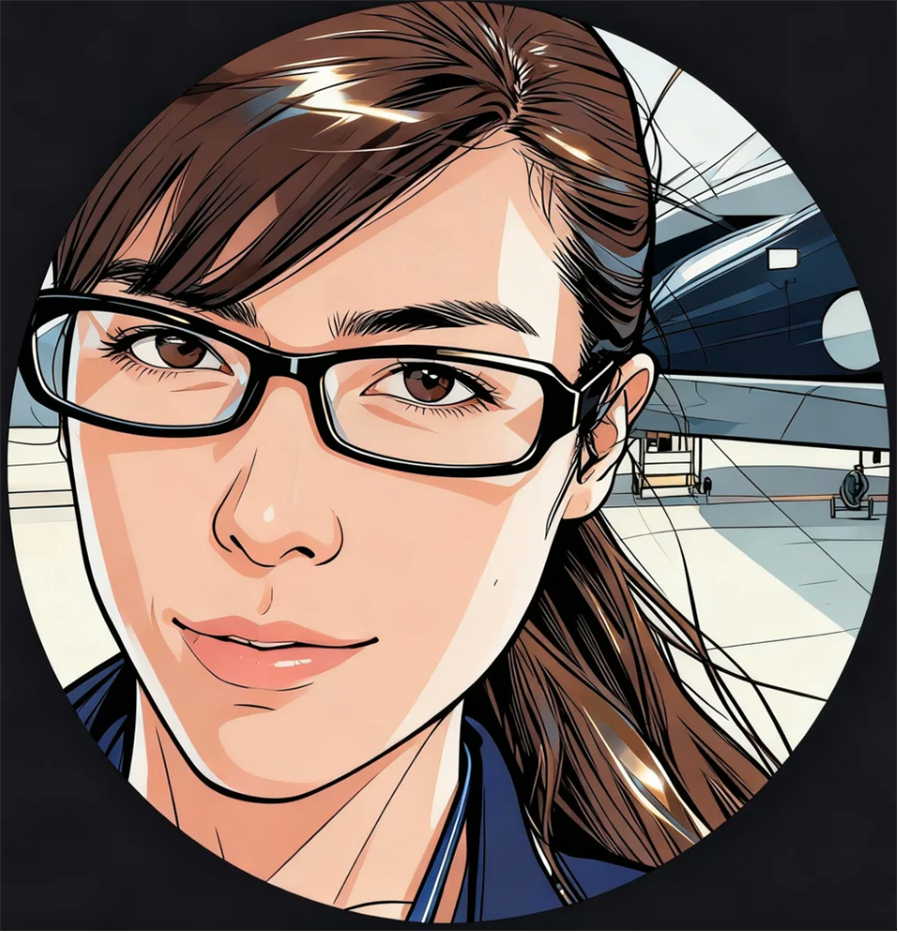
こんにちは、なおじです。
「迷惑行為」という言葉を、あなたは政治家の口から聞いたことがありますか?
自民党の小野田紀美経済安保担当相が、週刊新潮の取材にこの強烈な言葉を使って抗議しました。
すると、元TBSキャスターの杉尾秀哉議員が「言い過ぎだ」と反論。
政治家同士の対立に発展しています。
でも、ちょっと待ってください。
この騒動、実は私たち一般市民にも深く関わる問題なんです。
なぜなら、取材を受けたのは小野田氏本人ではなく、あなたや私と同じ「一般の人たち」だったからです。
地元の知人や同級生のもとに、突然週刊誌の記者が訪ねてきたら、どう感じますか?
報道の自由と個人のプライバシー。
どちらも大切な権利が、真正面からぶつかり合っています。
元社会科教師として35年間、民主主義を教えてきた私が、この問題の本質を読み解いてみましょう。
発端は地元からの「SOS」
事の始まりは、2025年10月26日でした。
小野田紀美氏が自身のX(旧Twitter)に投稿した一文が、瞬く間に拡散されたんです。
「週刊新潮の取材が来た」という連絡が、地元の岡山県や同級生から多数届いているというのです。
高市早苗首相のもとで経済安保担当相に起用されたばかりの小野田氏。
42歳の参院岡山選挙区選出議員です。
彼女のもとに寄せられたのは、悲鳴にも似た声でした。
「どこで個人情報が漏れているのか分からなくて怖い」
「気持ち悪い」
一般の方々が、突然の取材に動揺している様子が伝わってきますね。
週刊新潮の取材手法に疑問の声
小野田氏が特に問題視したのは、取材の「やり方」でした。
取材を断った人に対して、週刊誌側がこう追及したというのです。
「なぜ取材を断るのか、理由を述べてください」
これには驚きました。
一般人が取材を断ることは、当然の権利のはずですよね。
しかも、断った理由まで説明を求められたら、プレッシャーを感じて当然でしょう。
小野田氏は最後に、こう締めくくりました。
「このような迷惑行為に抗議します」
この言葉が、のちに大きな波紋を呼ぶことになります。
週刊新潮が反論「正当な取材活動です」
黙っていなかったのが、週刊新潮編集部です。
弁護士ドットコムニュースの取材に対して、こう回答しました。
「取材は小野田大臣本人の人物像を明らかにするため」
そして、きっぱりとこう言い切ったんです。
「迷惑行為などではなく、正当な取材活動です」
編集部の論理はこうです。
政治家の人物像を知ることは、国民の知る権利に応えるもの。
だから周辺取材も必要だ、と。
確かに一理ある主張ですね。
でも、取材される側の気持ちはどうなのでしょうか。
元TBSキャスター杉尾議員が参戦
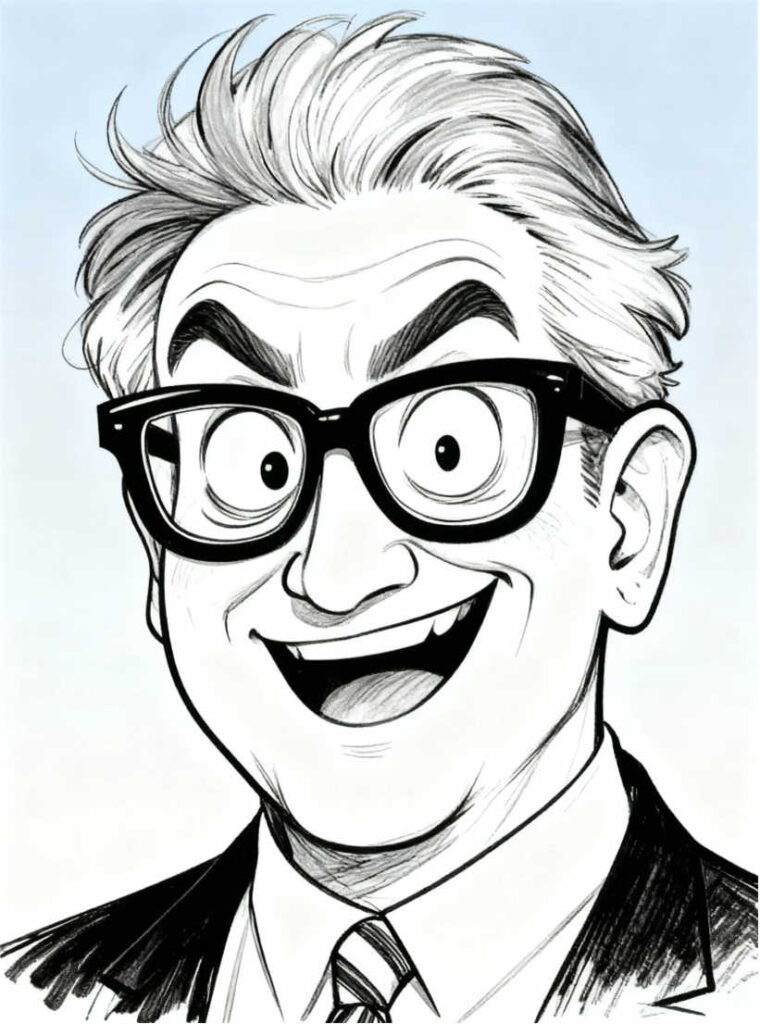
ここに第三者として登場したのが、立憲民主党の杉尾秀哉参院議員です。
68歳、元TBSキャスターという経歴の持ち主。
報道の現場を知る人物からの発言だけに、注目が集まりました。
「迷惑行為」は言い過ぎではないか
杉尾議員は10月28日、自身のXでこう述べています。
「どんな取材行為だったかは分からない」
そう前置きしつつも、続けてこう指摘しました。
「常識を逸脱したようなものでなければ、メディアの取材を『迷惑行為』と決めつけるのは言い過ぎではないか」
元メディア人らしい、報道を擁護する立場です。
権力はチェックされて当然?
杉尾議員はさらに、核心を突く主張をしました。
「特に権力の側にいるものはチェックされるのが当たり前なのだ」
そして最後に、こう締めくくったんです。
「私はこの投稿に強い違和感を覚える」
かなり強い言葉ですよね。
でも、私にはひとつ疑問が残ります。
杉尾議員は「どんな取材行為だったかは分からない」と言いながら、なぜ小野田氏を批判できるのでしょうか。
事実を確認せずに判断するのは、ジャーナリズムの基本に反しませんか?
維新の藤田議員は小野田氏に賛意

一方、日本維新の会の藤田文武共同代表は、小野田氏に賛同する投稿をしています。
与野党を超えて、政治家の間でも意見が真っ二つに割れているわけです。
この問題、そう簡単には答えが出せません。
あなたの疑問に答えます|Q&A
Q1:政治家への取材は本当に「迷惑行為」なのですか?
いい質問ですね。
政治家本人への取材なら、基本的には報道の自由の範囲内です。
なぜなら、政治家は「公人」だから。
国民から選ばれ、税金で給料をもらい、権力を行使する立場にあります。
だからチェックされるのは当然、という杉尾議員の主張にも一理あるんです。
ただし、今回問題となったのは、政治家本人ではありませんでした。
一般人である同級生や地元住民への取材だったことが、この騒動の核心部分です。
Q2:週刊誌は一般人に取材してもいいんですか?
法律上は、取材自体が禁止されているわけではありません。
報道の自由は憲法21条で保障されていますからね。
しかし、取材を受ける側には「取材を断る権利」があります。
これも憲法で保障された権利です。
問題は、断った後の対応でした。
「なぜ断るのか理由を述べよ」という追及は、倫理的にどうなのか。
私が教師時代、生徒たちによく言っていたことがあります。
「権利には責任が伴う」と。
取材する側にも、倫理的な判断が求められるはずです。
Q3:杉尾議員の「権力はチェックされて当然」は正しいですか?
この主張そのものは、民主主義の基本原則として正しいでしょう。
権力を監視することは、メディアの重要な役割です。
私も35年間、社会科教師として同じことを教えてきました。
でも、今回のケースには違和感があります。
なぜなら、「権力者本人」ではなく「周辺の一般人」が取材されたからです。
政治家の同級生は、自ら公人になることを選んだわけではありません。
ネット上でも「大臣相手ならわかるが、相手は一般人」という指摘が多く見られます。
権力監視と個人のプライバシー保護、このバランスをどう取るかが問われているんです。
なおじが見た本質|二つの権利の衝突
教師をやってきて、いつも難しいと感じたのが「権利と権利がぶつかったとき」の判断です。
今回の騒動も、まさにそれ。
片方には「報道の自由」と「国民の知る権利」があります。
もう片方には「プライバシー権」と「取材を断る権利」がある。
どちらも憲法で保障された、大切な権利なんです。
報道の自由は民主主義の土台
週刊新潮の主張を考えてみましょう。
「政治家の人物像を明らかにする」という目的は、確かに正当です。
投票する私たちにとって、政治家がどんな人物なのか知ることは重要ですからね。
学生時代の友人、地元での評判、人となりを知る手がかりは、周辺取材から得られることも多いでしょう。
メディアが権力を監視する役割を果たすためには、取材の自由が必要です。
これは民主主義社会の土台と言っても過言ではありません。
でも一般人のプライバシーは?
一方で、今回取材を受けた方々の気持ちを想像してみてください。
ある日突然、週刊誌の記者が訪ねてきたら。
「昔の同級生について教えてください」と聞かれたら。
しかも断ると「なぜ断るのか理由を言え」と追及されたら。
「どこで私の個人情報が漏れたの?」と不安になりませんか?
同級生や地元の知人は、政治家になることを選んだわけではないんです。
公人として注目されることに同意していない、私たちと同じ一般市民です。
教師時代に教えてきたこと
私が生徒たちによく言っていたのは、こんなことです。
「権利がぶつかったときは、どちらかを全否定するんじゃない。バランスを考えなさい」
報道の自由も大事。
でも個人のプライバシーも守られるべき。
この両立を目指すべきじゃないでしょうか。
たとえば、取材する相手を選ぶ判断。
政治家本人、側近、公式な場で発言している支援者などは、取材対象として適切でしょう。
でも、何十年も前の同級生まで追いかける必要があるのか。
断った人に理由を詰問する必要があるのか。
メディアには、こうした倫理的な判断が求められているはずです。
杉尾議員の発言で見えたもの
杉尾議員の発言には、もうひとつ気になる点があります。
「どんな取材行為だったかは分からない」と述べながら、小野田氏を批判したことです。
私が教師時代、生徒たちに口酸っぱく言っていました。
「事実を確認してから意見を言いなさい」と。
実際の取材内容を確認せずに「言い過ぎ」と判断するのは、ちょっと早計ではないでしょうか。
もしかしたら、常識を逸脱した取材があったかもしれない。
一般人が本当に恐怖を感じるような状況だったかもしれない。
それを確認せずに批判するのは、公平な判断とは言えませんよね。
元メディア人として報道を擁護したい気持ちは分かります。
でも、だからこそ事実確認の重要性を誰よりも理解しているはずです。
私たちはどう考えるべきか
この問題に、簡単な答えはありません。
でも、いくつか考えるべきポイントがあります。
まず、「政治家本人への取材」と「周辺の一般人への取材」は、分けて考える必要があるということ。
政治家はチェックされて当然です。
でも、その家族や友人まで同じように扱っていいのか。
線引きは難しいけれど、議論は必要でしょう。
次に、メディアには自主的な倫理規範が求められるということ。
法律で禁止されていなければ何をしてもいい、というわけではありませんよね。
取材対象を選ぶ判断、取材方法の配慮、こうした倫理的な姿勢が信頼を生みます。
そして最後に、私たち市民も当事者だということ。
明日、あなたの知人が政治家になったら、あなたも取材される可能性があるんです。
「自分だったらどう感じるか」という想像力を持ちながら、この問題を見つめたいですね。
ヤフーコメントに見る世論の反応
この騒動に対して、ヤフーコメントやX上では賛否両論が渦巻いています。
特に注目されたのが、杉尾議員の投稿に対する反応でした。
「本人ではなく、地元の同級生たちに取材って段階で『やらなくてもいい取材』じゃないですかね」という批判的なコメントが多数見られました。
また杉尾議員が「どんな取材行為だったかは分からない」と述べながら小野田氏を批判したことに対しては、「内容がわからないのに批判するのに強烈な違和感しか感じないんですが」という疑問の声も。
さらに「どんな取材であったかについては明記されてます。事実であれば常識を逸脱した迷惑行為かと思われます」との指摘や、
「小野田紀美大臣が相手ならわかるが、相手は一般人。だから『迷惑行為』と言われてます」という声が寄せられています。
一方で、報道の自由を重視する立場からは、権力者による取材批判への懸念も見られました。
全体としては、「一般人への取材」という点に焦点を当てた意見が多く、小野田氏の主張に理解を示すコメントが目立つ傾向が顕著でした。

まとめ
小野田紀美氏と週刊新潮、杉尾秀哉議員を巻き込んだこの騒動。
表面的には政治家とメディアの対立に見えますが、本質はもっと深いところにあります。
報道の自由と個人のプライバシー、どちらも民主主義社会に不可欠な権利です。
一方を犠牲にして他方を守るのではなく、両立の道を探る知恵が必要でしょう。
政治家はチェックされる覚悟を持つべきです。
メディアは倫理的な取材を心がけるべきです。
そして私たち市民は、こうした議論に関心を持ち続けるべきです。
なぜなら、健全な民主主義は、私たち一人ひとりの意識から生まれるものだからです。
あなたは今回の騒動、どう感じましたか?
【関連ブログ】
・小野田紀美の二重国籍問題、その真相は?|2016年発覚から2025年大臣就任まで
・安倍元首相「最後の投稿」が再び話題に|小野田紀美入閣で3年越しの約束実現
・小野田紀美の学歴・経歴|ゲーム会社から政治家への異色キャリアを徹底解説
・小野田紀美が防衛大臣にならなかった理由|経済安保大臣就任の真相を解説
・小野田紀美経済安保大臣抜擢の理由|42歳2期目の異例人事を徹底解説