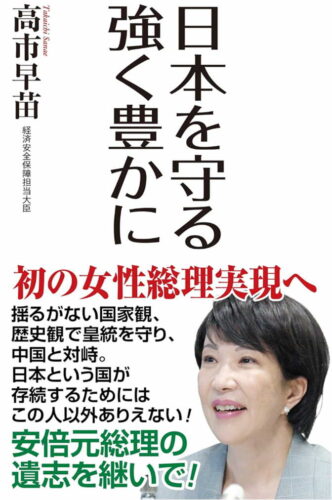志位和夫議長の批判と野党の反応
一方で、高市首相の非核三原則見直し論に対して、強い批判をした人物がいます。
共産党の志位和夫議長です。
志位議長は2025年10月27日、自身のXで
「高市首相は、『非核3原則』は『邪魔』だとして、『安保3文書』からの削除を求めていたことを自ら明らかにしていた。強い憤りを感じる」
と投稿しました。
そして「こんな人物に唯一の戦争被爆国の首相を担う資格はない」と厳しく批判したのです。
志位氏は以前から高市政権について「戦後のなかでも最悪の政権となる危険」「ファシズムの匂いただよう」などと警告を発しており、今回の報道で懸念がさらに強まったとしています。
長崎大学核兵器廃絶研究センターもまた、
高市首相の非核三原則見直し論に対し、「国家安全保障戦略からの転換を求めることを意味するか」「周辺国の反応でさらなる軍拡による負のスパイラルに陥るリスクを考慮しているか」
などの懸念を表明したのです。
志位氏批判が抱える論理的矛盾を徹底検証
ここで、志位和夫議長の批判そのものが抱える論理的矛盾について、冷静に分析してみましょう。
矛盾点①:中国・北朝鮮の核脅威への具体的対案の欠如
志位氏は高市首相を「首相の資格はない」と批判していますが、では共産党は中国の核弾頭が年間100発ペースで増強され、北朝鮮が核ミサイルで日本を威嚇している現実にどう対処するのでしょうか。
具体的な代替案を示さずに批判だけを繰り返すのは、無責任と言わざるを得ません。
「非核三原則を守れ」と主張するのは簡単ですが、それで国民の命をどう守るのか、その答えが見えないのです。
矛盾点②:「核の傘」依存と「持ち込ませず」の両立不可能性
日本共産党は日米安保条約の破棄を主張していますが、現実には日本は米国の「核の傘」(拡大抑止)に依存して安全保障を確保しています。
志位氏の批判は、この現実から目を背けています。
米国の核抑止力に依存しながら「持ち込ませず」を厳格に守るというのは、まさに高市氏が指摘する「構造的矛盾」そのものです。
有事の際、米軍が効果的に日本を防衛するためには、核戦力の柔軟な運用が必要になるでしょう。
その現実を無視して理念だけを主張するのは、「思考停止」と言わざるを得ません。
矛盾点③:感情論的批判と安全保障の現実との乖離
志位氏の「ファシズムの匂い」「首相の資格はない」といった表現は、感情的レッテル貼りに過ぎません。
高市氏が提起しているのは、「国民の命か、非核三原則か」という究極の二者択一の問題です。
これは感情論で片付けられる問題ではなく、冷静な分析と議論が必要な安全保障上の重要課題なのです。
被爆国日本の理念を大切にすることと、現実の安全保障上の脅威に対処することは、決して対立するものではありません。
両立の道を模索するために、タブーなき議論が必要なのです。
矛盾点④:過去の民主党政権・岡田克也外相の答弁との整合性
高市氏の編著『国力研究』でも指摘されていますが、民主党政権時代の岡田克也外相(当時)は国会で、核兵器搭載の爆撃機が国内に飛来するような事態が発生した場合、「非核三原則を守るかの判断はその時の政府の判断」と答弁しています。
つまり、有事の際には非核三原則が絶対ではないという認識は、実は立憲民主党の前身である民主党政権時代にも存在していたのです。
国を本当に守る立場(与党)に立てば、当時の民主党はもちろん、おそらく現在の国民も立憲も、同じように答えざるを得ないでしょう。
志位氏は高市氏を批判していますが、この岡田外相の答弁についてはどう考えるのでしょうか。
高市氏の主張と岡田外相の答弁は、本質的に同じです。
矛盾点⑤:議論そのものを封殺する姿勢
志位氏の批判で最も問題なのは、「議論すること自体を否定する」姿勢です。
民主主義国家において、安全保障政策について国民が議論することは当然の権利であり、義務でもあります。
「こんな人物に首相の資格はない」という人格攻撃的批判は、建設的な議論を封殺し、思考停止を強要するものです。
石破茂元防衛相が指摘したように、日本はこれまで「議論もせず」という「第四原則」で思考停止してきました。
志位氏の批判は、まさにこの思考停止を続けようとするものではないでしょうか。
Q&A:非核三原則をめぐる論点を整理
Q1: なぜ「持ち込ませず」が問題視されているのですか?
A: 日本は米国の「核の傘」(拡大抑止)に依存する安全保障政策を採っています。しかし、有事の際に米軍が核戦力を効果的に運用するには、日本の基地や領海への一時的な核持ち込みが必要になる可能性があります。「持ち込ませず」の原則がこれを妨げる場合、抑止力の実効性が損なわれるという指摘です。
Q2: 「核の傘」は本当に日本を守れるのですか?
A: この点は議論があります。米国の核戦力は海外や潜水艦に配備されており、必ずしも日本国内への持ち込みが必須ではないという見方もあります。一方、中国の核戦力が急増する中で、米国が自国の大都市への核攻撃リスクを冒してまで日本を守るか疑問視する声もあり、より実効的な抑止力の構築が課題とされています。
血を流さず、リスクを冒さず『守ってください』と、泣きつくだけの日本を、米国は、、自らの血を流して守るでしょうか。
この結果を想像しようとしないのか、想像できないのか…、どちらだと思います?
Q3: 非核三原則を見直すと、周辺国はどう反応しますか?
A: 中国や北朝鮮が日本の姿勢変化を口実にさらなる核軍拡を進め、「安全保障のジレンマ」に陥る危険性が指摘されています。また、韓国など他の同盟国も同様の動きを取る可能性があり、東アジア全体の核拡散につながる懸念があります。これは慎重な検討が必要な論点です。
Q4: 高市首相は2026年末の安保3文書改定で実際に削除するのですか?
A: 高市首相は2024年10月24日の所信表明演説で、安保3文書を2026年末までに改定すると明言しました。しかし、非核三原則は国会決議もされており、削除には大きな政治的反発が予想されます。現時点では不透明ですが、警戒する声が上がっています。
Q5: 被爆者団体はどう考えていますか?
A: 被爆者団体や市民団体は、高市政権が非核三原則を堅持するよう強く求めています。唯一の戦争被爆国である日本が核兵器に対する姿勢を後退させることは、被爆者の願いに反するだけでなく、国際社会における日本の平和国家としての信頼を損なうと懸念されています。
Q6: なぜ今このニュースが注目されているのですか?
A: 高市氏の編著『国力研究』自体は2024年9月に出版されていましたが、しんぶん赤旗が2025年10月27日付でトップ記事として報じたことで広く知られることになりました。高市氏が首相に就任し、安保3文書の改定権限を持つ立場になった今、過去の主張が現実化する可能性があるため、注目を集めています。
Q7: 志位氏の批判のどこが矛盾しているのですか?
A: 最大の矛盾は、中国・北朝鮮の核脅威が現実化している中で、具体的な対案を示さずに批判だけを繰り返している点です。また、日本が米国の「核の傘」に依存している現実を無視し、「持ち込ませず」の厳格な堅持を主張するのは、高市氏が指摘する「構造的矛盾」を認めないことに他なりません。さらに、感情論的な人格攻撃で議論そのものを封殺しようとする姿勢は、民主主義国家にふさわしくありません。
なおじの視点――非核三原則と安全保障、二つの「命」の板挟み
私は35年間、社会科教師として平和教育に携わってきました。
授業で広島・長崎の被爆者証言を扱うたび、生徒たちは深く心を動かされます。
「二度とこのような悲劇を繰り返してはならない」という思いは、世代を超えて受け継ぐべき価値観でしょう。
同時に、社会科教師として安全保障の現実も教えてきました。
C国の核弾頭が年間100発ペースで増え、北朝鮮のミサイルが日本を射程に収める現実を前に、「理念だけで国民の命を守れるのか」という問いからも目を背けられないのです。
高市首相が提起したのは、まさにこの「被爆国としての理念」と「現実の安全保障」という二つの「命」の問題です。
「国民の命か、非核三原則か」という問いかけは、感情的に拒否するのではなく、冷静に議論すべき課題ではないでしょうか。
もちろん、議論の結果として非核三原則を堅持するという結論もあり得ます。
しかし「議論すること自体がタブー」という姿勢は、民主主義国家として健全とは言えません。
志位氏のような感情論的批判で思考停止するのではなく、安全保障専門家たちが口をそろえて指摘する「矛盾」に、私たちは向き合う勇気が必要です。
まとめ――高市早苗氏の非核三原則見直し論、タブーなき議論を
高市早苗首相の「非核三原則は邪魔」という発言は、単なる過去の主張ではなく、2026年末の安保3文書改定という具体的な政策決定に影響を与える可能性があります。
この問題提起は、石破茂氏(元防衛相・元首相)や元国家安全保障局次長らも行ってきた、日本の安全保障政策の「構造的矛盾」の指摘です。
中国の核弾頭が2030年までに1000発を超え、北朝鮮の核ミサイルが日本を射程に収める現実の中で、「核の傘」の実効性をどう確保するかは切実な課題となっています。
一方で、志位和夫議長の批判は、具体的な対案を示さず、感情論に終始し、議論そのものを封殺しようとする点で、論理的矛盾を抱えています。
「平和の理念」と「安全保障の現実」――この両立は容易ではありません。
しかし、だからこそタブーなき議論が必要なのです。
感情論や思考停止ではなく、冷静な分析と建設的な対話を通じて、唯一の戦争被爆国である日本にふさわしい安全保障政策を模索していく時期に来ています。
志位氏のような批判に屈して議論を放棄するのではなく、国民一人ひとりが真剣に考え、語り合うことこそが、民主主義国家の責任なのではないでしょうか。
関連記事はこちら
- 高市首相 所信表明 ヤジ問題騒然!本当の理由と全容
- 安倍晋三と高市早苗の深い関係とは?保守路線の真相を徹底解説

【関連ブログ】
高市早苗の税制改革を徹底解説|給付付き税額控除・年収の壁・ガソリン減税の詳細